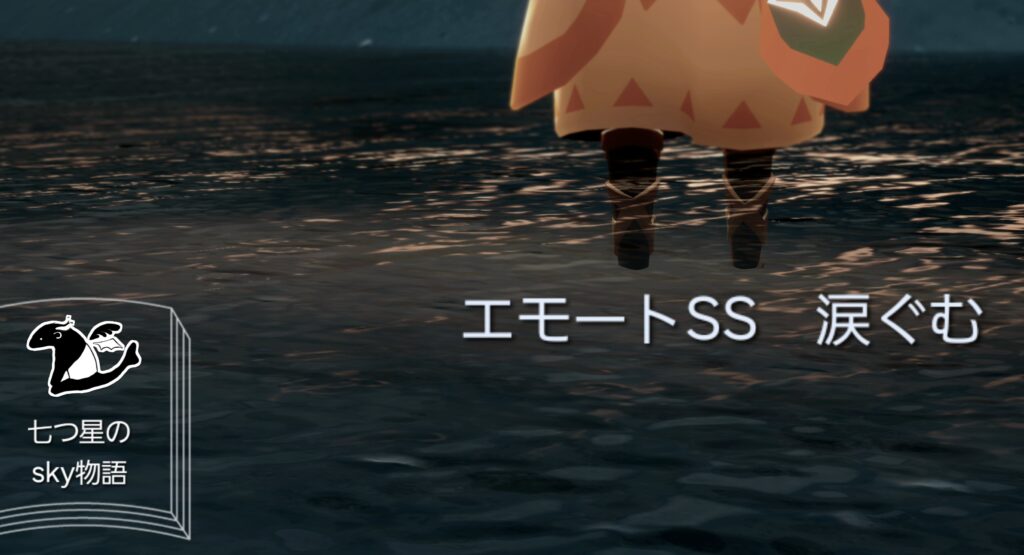どれだけ長く生きていても、目の前で仲間を永遠に失うという経験だけは、決してない。
使命を果たして身体が砕けたとしても、それは新しい祝福へと誘われ、光り輝く魂となって、友や生命たちと天を飛ぶ。
だから、『仲間を喪う』という悲しみは、永遠に知るはずのない感情なのだ。
雨林の墓所、地表の出入り口を蝕む闇に塞がれた、小さな洞窟の中。蹲る光坑夫の記憶に火を灯す。
精霊の記憶は、何度でも同じ光景をみることができる。ここで何があったのかわかるようになったのは、何度目のことだったか。
四人の坑夫がこの洞窟に閉じ込められ、内二人が落盤に巻き込まれる。次の記憶には二人の姿はなく、代わりに二つの小さな石積みが増え……もう一人が闇に蝕まれる。次の記憶には、小さな石積みは三つに増えて、一人立ち尽くす光坑夫の姿がある。最後に見る光坑夫は僅かに高くなった洞窟の奥で、濡る水面を避けるように膝を抱えて蹲っている。
記憶を解放する瞬間、光坑夫が落涙する様子を見守ることになる。だが、何故かこの時、必ず、星の子自身は光坑夫のいる僅かな高台から水面へと降ろされる。
ポロポロ、と涙を零す光鉱夫を見上げる。
その背後は、星の子が旅する現在まで残された三つの墓碑がある。記憶の中で見た、石を積んだだけの小さな石積みとは違う、大きなものだ。きっとだれかが、ここに墓碑を三つ建てていたのだろう。そしてそれは、長い年月の後に風化して折れてしまっている。
涙ぐむ、という感情を、この精霊は教えてくれる。
ここで、この記憶の流した涙が、もしも現実にあったなら。数多の星の子が紡いだ記憶は、きっと湖となっただろう。今足元を濡らすこの水が、すべてが涙であるかのように錯覚してしまうほど。仲間を喪うことは、一人残されることは、辛いことなのだと。
物言わぬ墓碑を滲む視界に捉え、孤独に立ち尽くし、ついには膝を抱えて、もう一歩たりとも動けなくなる。その孤独と同じところに踏み入ることは許されず、寄り添うことさえ叶わない。
光坑夫の魂は小さな青い光となって消えていく。
そうして、一人、この暗い場所に残されて。
ひたひたと、この足を絡め取る冷たさが悲しみだと、何よりも雄弁に教わった、気がする。
この作品は、2021年skyエモートSS企画でXに投稿したものを加筆・修正したものです。
2025年11月skyArtFestにて、折本にして無料配布しました。
あとがき&解説はこちら